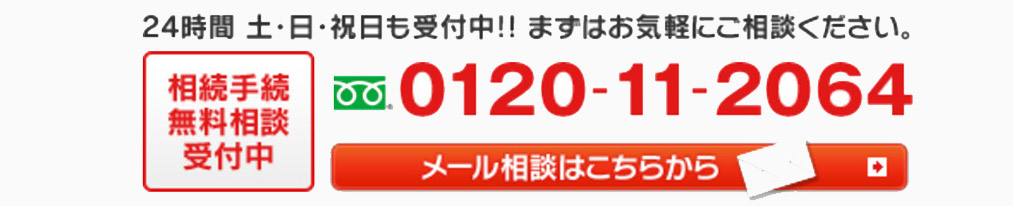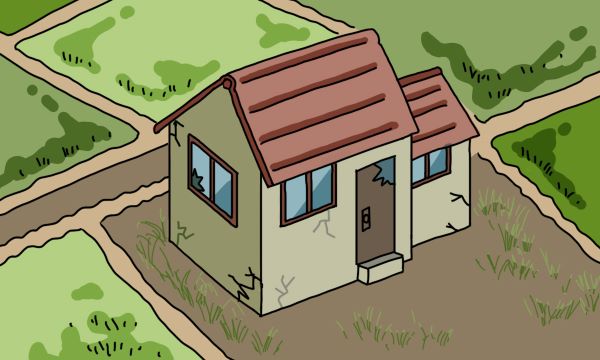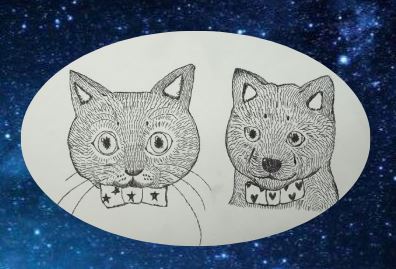相続コラム– category –
-

迷子の土地 全国で拡大
土地の持ち主や境界が不明のまま、有効活用が滞るケースが各地で相次いでいる。特... -

「おひとりさま」に保証人の壁
単身の高齢者が身元保証人がいないことを理由に、介護施設や病院への入所、入院を... -

配偶者や介護者への優遇措置を検討
民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会の部会は、中間試案をまとめた。来年... -

農村の空き家紹介サイト 神戸市が開設
神戸市は市内の農村地域への定住者の呼び込みに取り組む。農村部の空き家を紹介す... -

深刻な争い解決へ整備
民法の一部である相続法の改正作業が進んでいる。政府は来年の国会に提出する構え... -

実家の相続放棄 急増
住む予定がない実家などの相続を放棄する人が急増している。維持費用や固定資産税... -

相続空き家 売るなら早く(2)
空き家の対応に悩む人の間で最近注目されているのが、相続放棄だ。財産を引き継ぐ... -

ペット残して逝けない
13年施行の改正動物愛護管理法で、飼い主はペットが命を終えるまで責任を持って飼... -

コンビニで戸籍情報
税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度が始まるのを機に、熊本市や福島県郡... -

認知症者の事故責任 補償
認知症の男性による列車事故の責任をその家族が負うべきかどうかを争う裁判が話題...