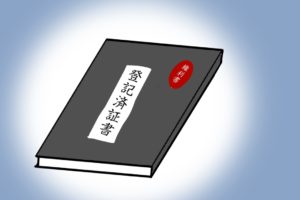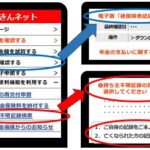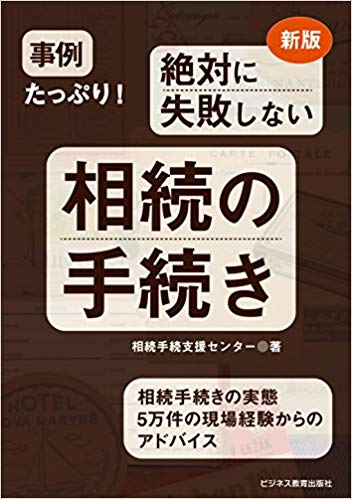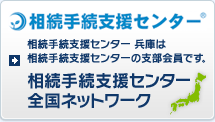京都大学こころの未来研究センター教授兼大学院人間・環境学研究科教授のカール・ベッカー氏は、日本人の死生観について、次のように述べています。
日本の歴史を見ていくと、災害が多く死が身近だった時代は、老・病・死をどう乗り越え消化できるかといった知恵があり、宮本武蔵、二宮尊徳などの死を視野に入れた生き方などがそれを物語っていました。その流れを受け、戦前までの日本は、死を自然の摂理・次の世への出発と考え、死を怖がらない社会だったのに、戦後1970~1980年代には、逆転し、死が知らない怖いものになりました。
病院死が戦前2割だったのが、8割にもなり、身近に死をみとる経験が減ったことが大きな原因です。しかし、そもそも病院は死をみとる場所ではなく、病気を治す場所。病気と闘って勝つ見込みがない場合は、どういう末期を過ごしたいのかをもっと素直に考えたいものです。
日本の家庭には、仏壇があり、先祖を思い出しながら大事な相談や報告をしている。先祖の知恵を心の中によみがえらせて守っているわけなので、自分が死んでもその意識や影響が続く可能性を考えると死はすべての終わりではないのです。そう思えば、個別の死を乗り越える力や勇気がわいてきます。
(平成25年5月25日 日経新聞より)
日本には、もう一つ、「家系図」というものがあります。家系図⇒家系という大きな流れの中で自分の存在を見て、先祖の恩恵を思い出し、「次は自分の番、できる範囲のことをして、次世代にバトンタッチしよう」と自然に思えるようになります。
自分の死について考えることで、今生きている日々を一日一日大事にしていくことができるのです。